仕事で成功する人と、そうでない人の違いは何でしょうか?
それは「センス」です。
センスと聞くと、才能やひらめきを思い浮かべるかもしれません。
でも、仕事におけるセンスとは、知識と経験に裏打ちされた「本質を見抜く力」のことを指します。
どんなに優れた技術があっても、それを正しく使いこなすセンスがなければ、成果にはつながりません。
明治時代、日本が西洋の技術と向き合ったとき、福沢諭吉らは単なるスキルではなく、その背景にある思想や哲学を学ぼうとしました。
彼らの姿勢には、現代のビジネスにも通じるヒントがあります。
では、仕事における「センス」とは具体的に何なのか? どうすれば磨くことができるのか?
この記事では、歴史的な視点も交えながら、仕事で成果を上げるために必要なセンスについて深掘りしていきます。
仕事に求められる「センス」とは?

人類は古来より、技術を手に入れ、磨いてきました。
技術は、生活を豊かにする道具にもなれば、社会に傷を与える危険な武器にもなります。
その違いを決めるのは、「センス」です。
ここでいうセンスとは、単なる感覚ではなく、知識と想像力に裏打ちされた本質を見抜く力のことです。
明治の知識人が示した技術活用の本質
仕事においても、センスのある人は単なる技術者ではなく、技術の本質を理解し、それを適切に活用できる人です。
明治時代、日本が西洋の技術文明と向き合ったとき、福沢諭吉をはじめとする知識人たちは、単なる技術の導入ではなく、その背景にある思想や哲学を理解しようとしました。
それは、技術と想像力が調和した瞬間でした。
現代の仕事に求められる「センス」とは?
しかし、現代はどうでしょうか。
情報技術の発展は、かつての産業革命を超えるスピードで社会を変えています。
新しいツールが次々と登場し、ビジネスの現場でもAIやデータ分析などが不可欠になっています。
でも、これらの技術を使いこなすには、単なるスキル以上のものが求められています。
技術を扱う人間の心得——老技術者の言葉
昔のことですが、京都の町家で出会った老技術者がこんな話をしてくれた。
「技術は使う者次第で神にも悪魔にもなる。それを見極める目を持たない者に、新しい技術を扱う資格はない」
これは仕事にも通じるのではないでしょうか。道具を持つだけでは意味はありません。大切なのは、それをどう使うかを見極める「センス」なのです。
仕事のセンスを磨くために大切なこと
情報社会では、表面的なスキルを習得することに目が向きがちです。しかし、大阪の商家に伝わる家訓にこうあります。
「新しきを知らざれば商い成らず、古きを忘れれば人に非ず」
これは、単に新しい技術を取り入れるだけではなく、そこにある本質や背景を理解しなければならないということを示しています。
技術の進化とリスク——歴史が教える教訓
技術が進化するほど、その誤用によるリスクも高まります。
名刀ほど使い手を選ぶように、現代の技術もまた、適切な知識と心得を持つ者だけが正しく扱えるものです。
歴史を振り返ると、技術の頂点に達した文明が突然崩壊しています。バビロニアやマヤ文明など、彼らは高度な技術を持っていたが、それを制御する「知恵」を失ってしまったのかもしれません。
現代社会においても、この教訓を忘れてはならないのです。
仕事で成功するための「センス」とは?

技術の力を正しく活かすためには、知識と想像力、そして何より、その技術が持つ二面性を理解することが求められています。
仕事における「センス」とは、まさにこの本質を見抜く力のことではないでしょうか。
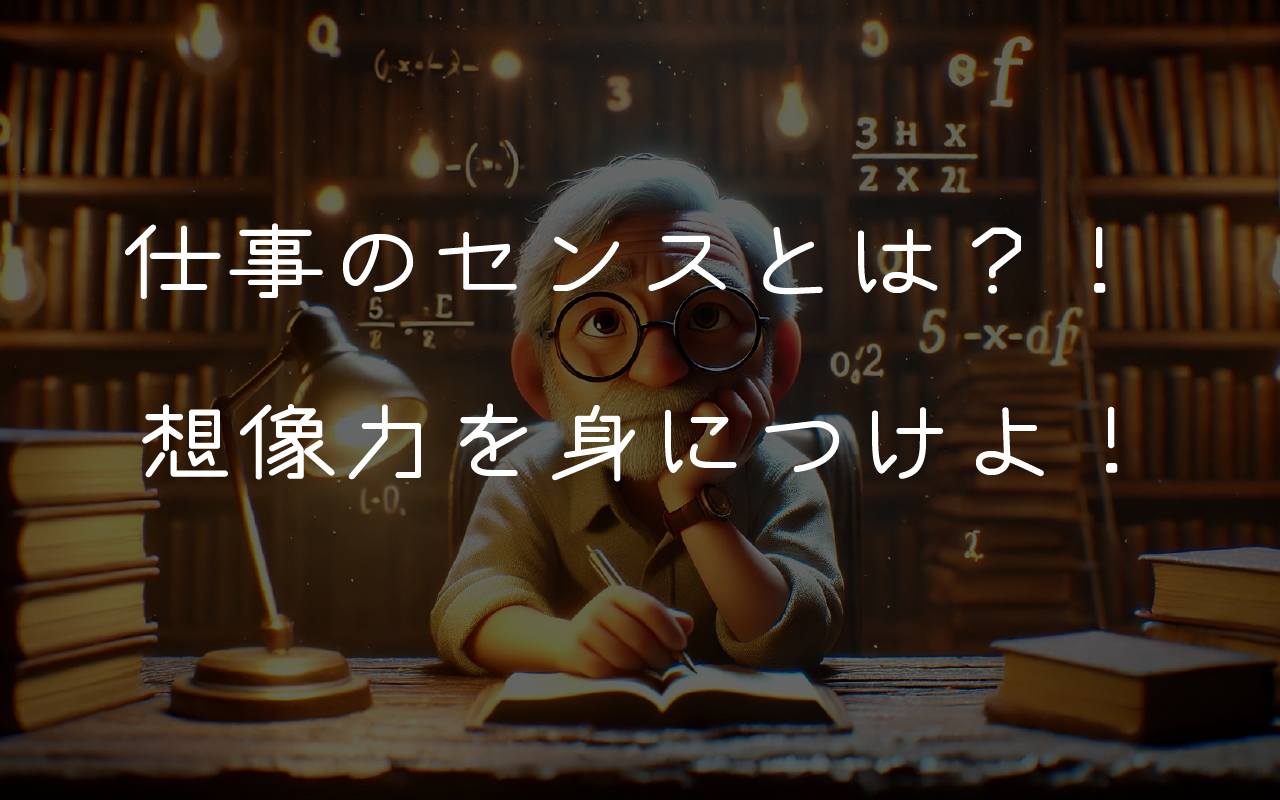
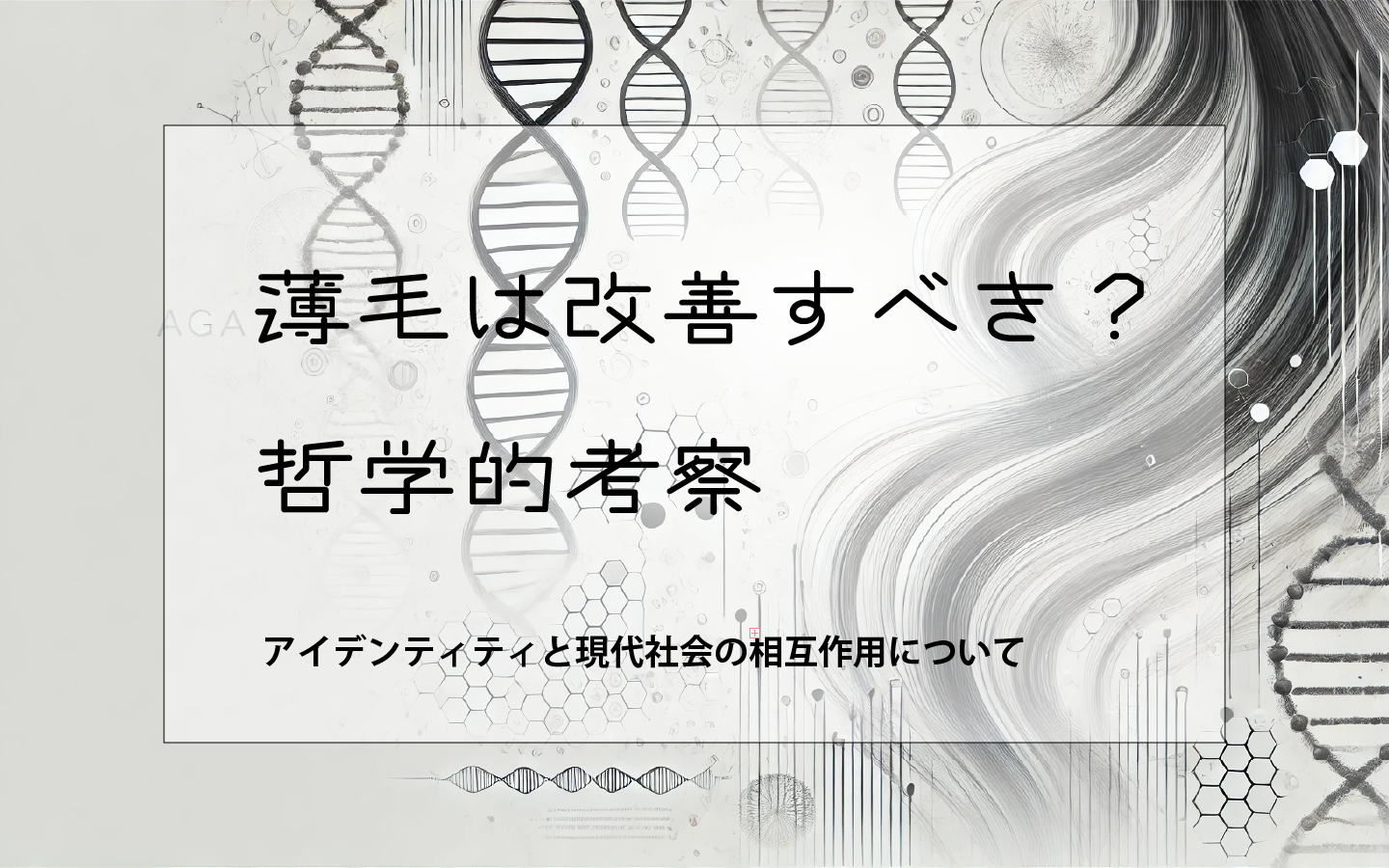
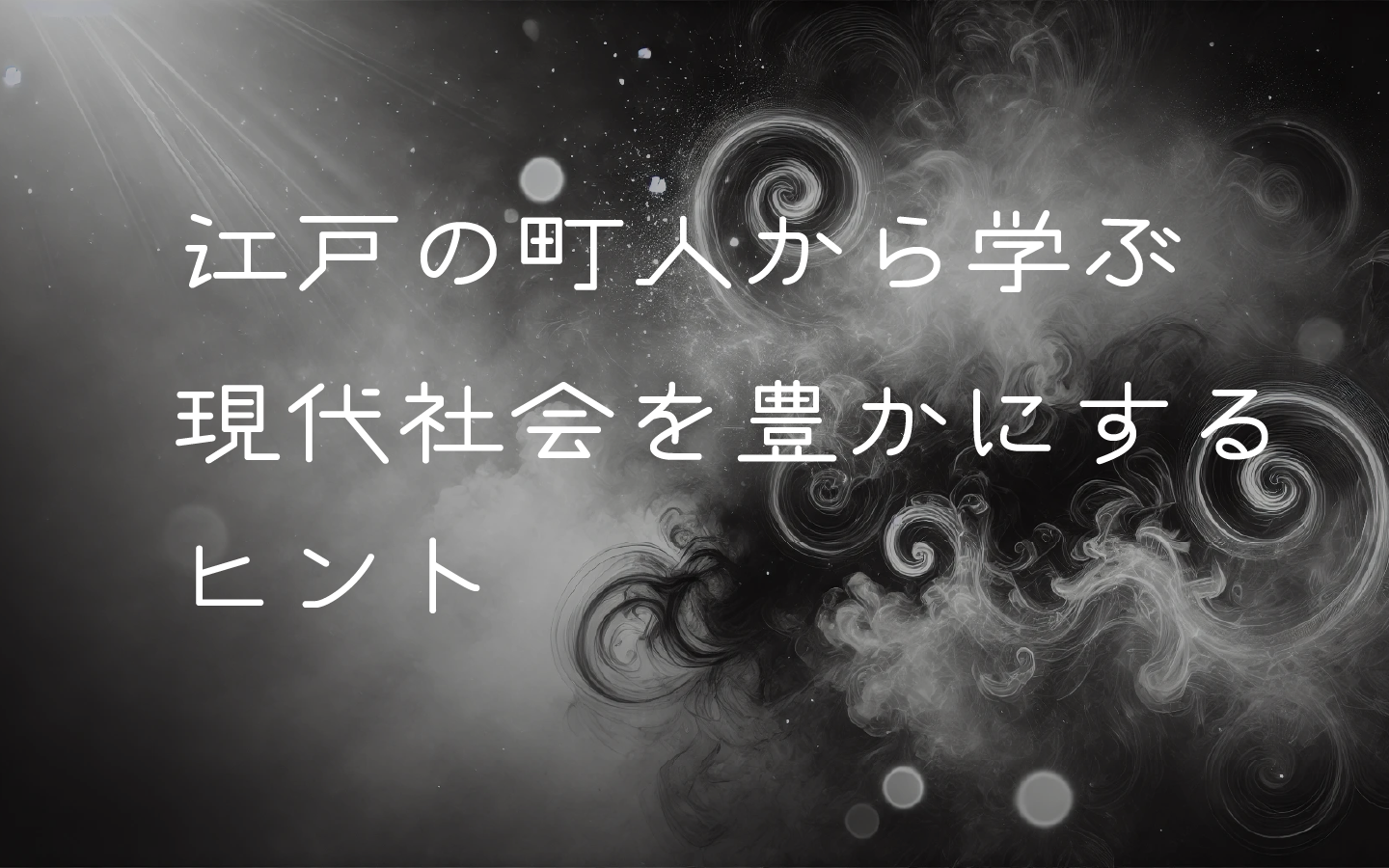
コメント