過去の産業革命と比べ、IT技術の発展スピードは驚異的な速度である。革新的な技術が次々と生まれ、まるで人智を超えた速度で社会が進化しているようだ。
現代を生きる僕たちは、これまでの人類が経験したことのない速さで変化に適応することを求められている。まさに、未曾有の試練に直面しているのだ。
僕は昭和生まれではあるが、まだ技術の進歩について行けている。でも、一瞬でも気を抜くと置いていかれる恐怖がある。
21世紀を生きる昭和世代へ
僕たちが子供の頃に夢見た『21世紀』が、今まさに現実のものとなっている。
昭和時代に思い描いていた未来社会とは異なるが、確実に技術は進化し、デジタル社会が当たり前のものとなった。
2000年代初頭こそ、まだ昭和の雰囲気が色濃く残っていたが、それから20年余りでスマートフォンやAIの進化によって、社会は加速度的に変化している。
この技術の進歩は、僕たちに利便性をもたらす一方で、適応できる人とそうでない人との間に格差を生んでいる。
もはや「昭和世代だから」「今さらデジタルは苦手だから」と言っていられない時代なのだ。
デジタル社会の歴史:昭和世代はどう変化を見てきたか
振り返ってみると、1990年代後半から徐々にインターネットが広がり始め、2000年代にはほとんどの企業でパソコンの導入が進んだ。
あっという間に、業務のデジタル化が進み、昭和世代も仕事でパソコンを使うことが一般的になった。
2010年代に入ると、スマートフォンが僕たちの生活を劇的に変えた。知らない土地を歩くための地図、知識欲を満たすための図鑑や辞典、さらには昭和世代の青春の一部であったエンタメコンテンツまで、すべてがスマホ一つで完結する時代となったのだ。
「デジタルは関係ない」はもう通用しない
しかし、いまだに「デジタル化なんて関係ない」「今までのやり方で十分」と考える昭和世代がいる。
特に50代以上の人々の中には、新しい技術に背を向け、従来の方法で生活を続けることにこだわる人も少なくない。
もちろん、アナログの良さは否定しないし、昔ながらのやり方でも生きていくことは可能だ。
しかし、問題はその考えが周囲に負担を強いることだ。デジタルが苦手なために、スマホやパソコンの設定を子どもや若い同僚に頼んだり、オンラインサービスの使い方を家族に聞いたりしている人は少なくない。
そのたびに「こんなの簡単だから自分でやれよ」と内心思われている確率が高い。
一つ一つの頼みごとは些細なものかもしれない。しかし、これから新しい技術が次々と生まれる中で、その依存度は増えていく。
つまり、デジタルを避け続けることは、自立を放棄し、周囲に負担をかけ続けることと同義なのだ。
AI時代にどう向き合うべきか
近年では、人工知能(AI)の進化が著しい。
ChatGPTをはじめとする生成AIが登場し、僕たちの働き方や生活を劇的に変えつつある。これらの技術を理解し、活用できる人材は今後ますます重宝される一方、対応できない人は社会から取り残される可能性がある。
「AIなんて自分の生活に関係ない」と思うかもしれない。
しかし、日本は少子高齢化が進んでおり、将来的には介護やサービス業の多くがAIやロボットに依存することになるだろう。そのとき、「機械が苦手だから」「ITはよく分からない」などと言っていると、時代遅れの老害として扱われかねない。
新しい技術を恐れるのではなく、少しずつでも学び、触れてみることが重要だ。
デジタルに慣れるために今できること
では、どうすれば昭和世代がデジタル社会に適応できるのか?
まずは興味を持つことが第一歩だ。
具体的には、スマートフォンで何ができるのかを調べ、実際に使ってみることが大切だ。例えば、以下のようなことを試してみるのもよい。
最初は戸惑うことも多いかもしれない。しかし、試行錯誤を繰り返すことで、少しずつ慣れていくことができる。
「できない」ではなく「試してみる」
最も大切なのは、「できない」と諦めるのではなく、「まずは試してみる」という姿勢だ。
誰もが最初は初心者であり、年齢は関係ない。むしろ、昭和世代は豊富な人生経験を活かして、新しい技術の本質的な価値を理解できる立場にあるとも言える。
デジタル社会への適応は、もはや選択肢ではなく必須のスキルとなっている。しかし、これは危機であると同時にチャンスでもある。新しい技術を受け入れ、活用することで、より便利で快適な生活を手に入れることができる。
未来へ向けて:昭和世代だからこそできること
デジタル技術を学ぶことで、自立した生活を維持し、次世代に負担をかけずに生きることができる。そして、昭和世代が持つ豊富な経験と知恵を、新しい時代に適応させることで、より価値のある未来を築くことができるのだ。
時代は変わる。しかし、その変化に対応できるかどうかは、自分自身の意識次第である。デジタル社会に適応することは、未来の自分への投資であり、より良い人生を送るための鍵となるのだ。
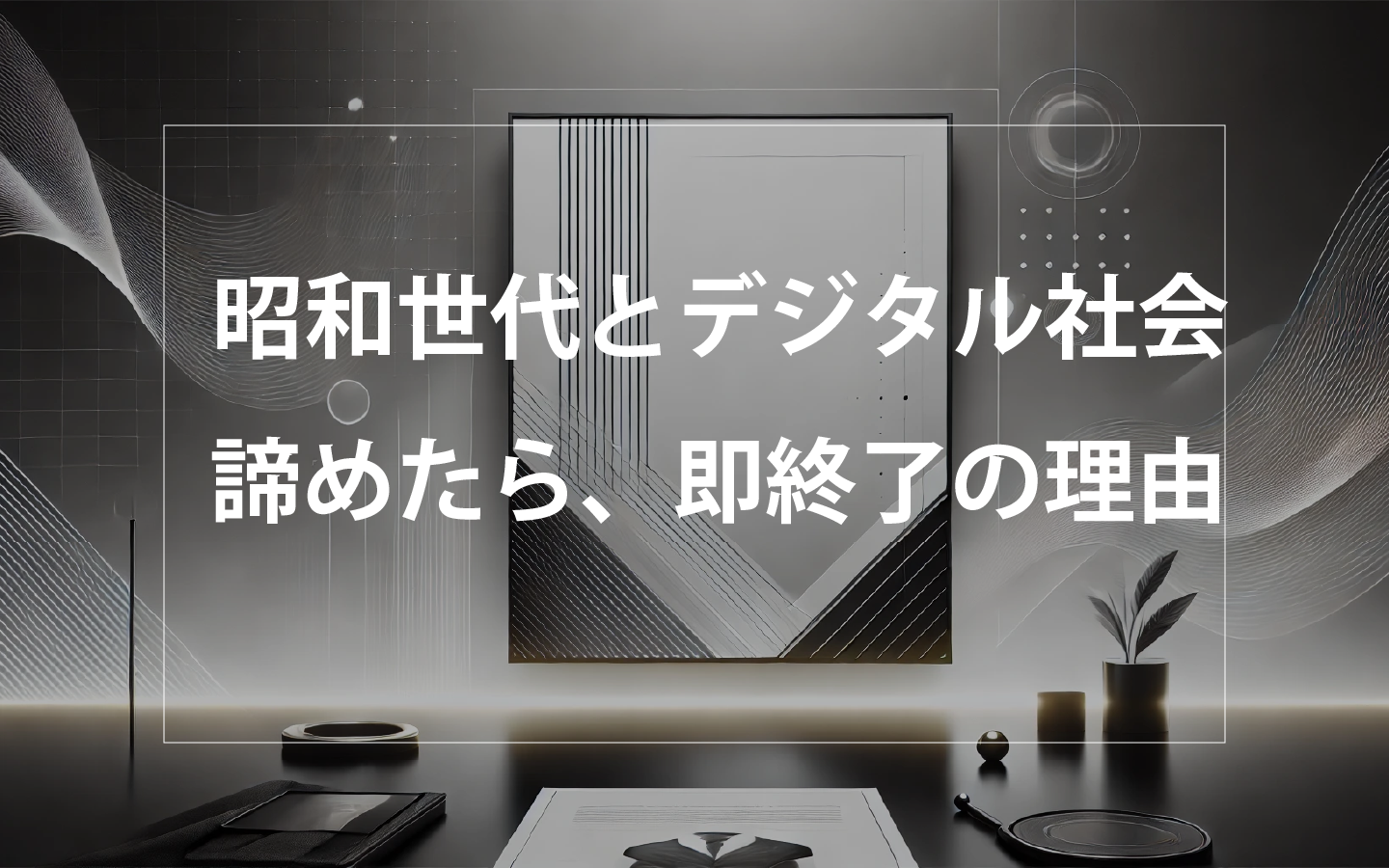
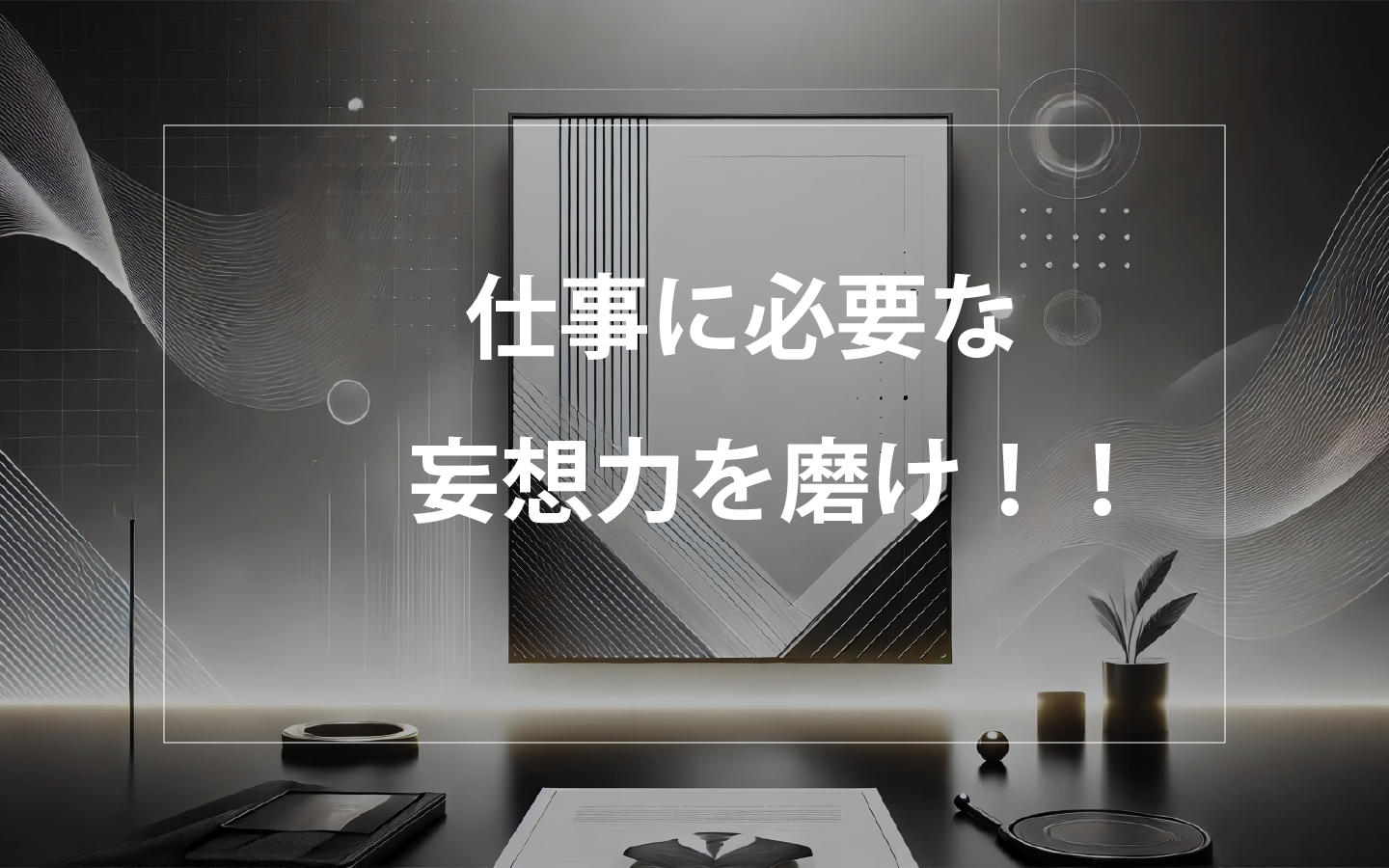
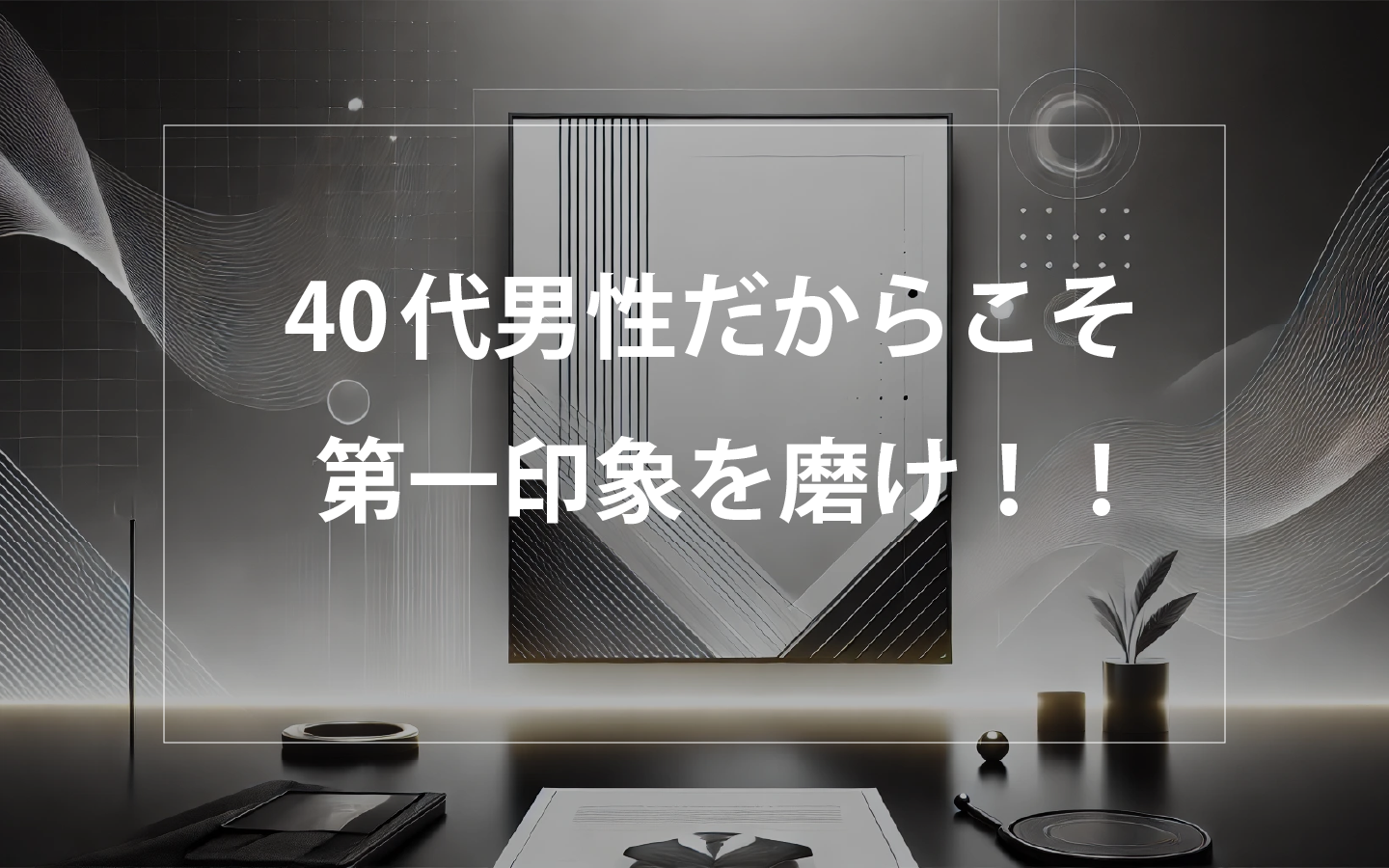
コメント